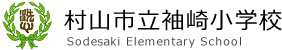令和6年度児童の活動
夏休み前最終日(7月26日)
明日から夏休みに入ります。
子どもたちは、今日も、学習のまとめや夏休みの準備を頑張っています。
1年生は、夏休みの生活表と目標を書いていました。
5年生は、稲作について調べたことを発表していました。
明日からの長い休み。子どもたちの成長が楽しみです。

絵が上手になりたい

わかったことは…
ステップアッププロジェクト(7月25日)
4年生以上は、今年度ステップアッププロジェクトに取り組んでいます。
これは、「個人総合」ともいうべきもので、一人一人が自分の「好き」や「知りたい」をとことん追究する学びです。
テーマは本当にそれぞれですが、共通するのは、子どもたちが非常に生き生きと取り組んでいること。
始めたばかりなので、追究に足るテーマを立てることや、うまくいかないときの修正方法については課題が多いですが、まずはやってみなければ何も始まりません。
トライ&エラーで少しずつ力をつけていくことができるよう、進めていきたいです。

演奏にチャレンジ

日本の山について調べています
授業参観(7月24日)
今日は、今年度2回目の授業参観です。
子どもたちは、心なしか、朝からそわそわしているようでした。
おうちの人を見つけると、恥ずかしそうな嬉しそうな、何とも言えない笑顔。
でも、授業が始まると、一転、真剣な表情で学びに向かいました。
何も制限がない状態で授業参観ができること、本当にありがたいと思っています。

書いた絵日記を紹介し合います

修学旅行の様子を伝えています
楽しく安全な夏休みを(7月23日)
今日は、夏休みのくらしについて話がありました。
火や水や車の事故、不審者、熱中症に気を付けて、楽しい夏休みを過ごしてほしいです。
特に今年は、すでに各地で水の事故や熱中症の搬送が相次いでいます。
危険を察知し、自分の命を自分で守る力が必要ですね。
今日、1年生は絵日記を書いていました。
夏休みの練習かな?

しっかり聞いて安全な夏休みを

書くのが楽しそう
夏休み前の総復習(7月22日)
夏休みまで、あと5日。
子どもたちは、復習に一生懸命取り組んでいます。
算数の復習問題。英語の既習表現の活用。テストも頑張っています。
一人一人が自分の成長を実感できることを願っています。

この問題の解き方は…

今まで学んだ表現を使って自己紹介
1,2年 そでさきたんけん 市民センター(7月19日)
今日は、雨で何度も延期していた、1,2年生活科の「そでさきたんけん」で袖崎市民センターに行きました。
お話を聞いてメモしたり、質問したり。
そのあとは、市民センターわきにある遊具や広場で遊びました。
子どもたちの身近にある市民センターですが、改めて訪問するとたくさん発見があったようです。

お話を聞いてメモします

楽しい!
全校読書2(7月19日)
昨日、今年度2回目の全校読書を行いました。
一人一人お気に入りの本を選んで、じっくり読みました。
本の世界に浸る素敵な時間が流れていました。

静寂の中で

いい時間です
見て動かして感じて考えて(7月18日)
3年生は、理科「ゴムの働き」を調べる実験をしています。
ゴムを引っ張る長さが、車の進む距離にどう関係するのか?
実験をしながら記録を取り、その結果から考えます。
2年生は、国語「思わず読みたくなる本の紹介をしよう」の学習。
自分の発表の様子をタブレットで撮影し、見返しています。
聞き手を見て発表しているか、本の見せ方はどうか、声は届くか?
自分の姿を自分で見て修正します。

これならどうだ?

思っていたのとちょっと違うなあ
市教育委員会学校訪問(7月17日)
今日は、村山市教育委員会からたくさんのお客様をお迎えしました。
いつも通り元気いっぱい学ぶ子どもたちに、お客様は、「エネルギーがあるね!」と驚かれていました。
ICTを活用したり、友達ときき合い、支え合いながら学んだりする様子も見ていただきました。

(英語を聞いて)わかった!消しゴムだ!

できるだけ図るところを少なくして描くには…
5,6年修学旅行(7月16日)
7月11日ー12日、5,6年生が修学旅行に行ってきました。
行先は、仙台、松島方面です。
行きは仙山線を利用しました。雨のため遅延し、少々焦りましたが、羽前千歳駅で無事に予定通り乗り換えることができました。
仙台市内のホテルに荷物を置いた後、班別研修。
八木山動物園とベニーランドに行きました。行きも帰りも地下鉄を利用。友達と相談しながら乗る電車を探しました。
ホテルでは、おいしい夕食をたくさん食べました。
2日目は、貸し切りバスで移動。
はじめにうみの杜水族館に行きました。
そのあと、遊覧船に乗って松島観光をし、松島では、五大堂や瑞巌寺など歴史的建造物を見学しました。
最後は、震災遺構荒浜小学校を訪れ、当時の校長先生だった方から、あの日何があったかをお聞きしました。
子どもたちは真剣に耳を傾け、家族、友人、そして今を大切に生きることを学びました。

津波が教室を襲いました

面白い形の島がたくさん

雨も上がって、最高!
校内オリエンテーリング(7月10日)
昨日、洗心委員会の企画で、全校生参加の校内オリエンテーリングが行われました。
子どもたちは、ユリノキ班ごとに、写真を手掛かりにして校内のある場所をさがし、近くに貼られたキーワードを探します。
それをつなげると、一つのメッセージになるという仕掛けです。
みんな、記憶力とチームワークを発揮して、楽しく活動していました。
話し合いを重ねて、楽しい企画を準備してくれた洗心委員の皆さんに感謝です。

わかった!あそこだ!

どこにキーワードがあるのかなあ。
基礎を学ぶ(7月9日)
連日、梅雨らしい天気です。
子どもたちは今日も頑張って学んでいます。
1年生はひらがなの練習。小さい「や」「ゆ」「よ」「つ」のつく言葉の学習です。
6年生は割合。「もとにする量」という、大変重要な概念を学んでいます。

真剣な表情

割合を求めるには…
七夕の願い事かなうといいな(7月8日)
7月7日は七夕。子どもたちは、生活科の学習で七夕飾りをつくりました。
「海に行きたい」
「大きくなったら考古学者になりたい」
などなど、それぞれの願い事を短冊に記して飾りました。

願い事、かなうといいな
それぞれが学ぶ(7月5日)
友達と意見を交流して、より深く学ぶのは価値あることです。
自分の考えを持つときに、友達と支え合うのも大切なことです。
そしてまた、友達がそばにいて、その気配を感じながら、それぞれが黙々と学びに向かうことも必要と思います。
それは、一人きりでする勉強とはまた違います。
教室で、仲間と共にいるからこそできる学びです。

自分の課題にむかって

調べたことを書く
水泳教室(7月4日)
今日は、東根市にあるスイミングスクールの先生を講師としてお招きし、水泳教室を行いました。
下学年はまず、顔を水につける、水中にもぐることから。そして、体をまっすぐにして進む練習をしました。
上学年はクロールの泳ぎ方を習いました。
クロールは、手のかき方がポイントです。
講師の先生の手の動きをよく見て、自分も繰り返し動かした後、実際に泳いで確かめました。
短い時間でしたが、専門の先生の指導でポイントがつかめたようです。
ICTを文房具のように使う(7月3日)
インターネットで資料を検索したけれど漢字が読めなくて内容がわからない、という時、以前は紙に印刷して一つ一つにふりがなを振って…という手間が必要でした。
また、検索ボックスに文字を打ち込みたいけれど、キーボード入力をまだ覚えていなくて入力できない、ということもありました。
今は、音声読み上げ機能、音声認識入力機能を使えば、まだ習っていない漢字が使われていても資料を読んで使うことができますし、キーボード入力ができなくても検索ができます。
漢字やキーボード入力はもちろん必要なので、これから繰り返し学んでいきます。
が、それらが未習であることが障害になって情報が収集できない、ということはほぼなくなりました。
情報を手に入れることはますます簡単になりました。
これからは、自分で課題を見つけること、課題解決のために手に入れた情報を使って、自分で考えることが大切になります。

音声読み上げを使って…

検索ボックスに入力するには
読み聞かせ(7月2日)
今日は、保護者の方から、今年度2回目の読み聞かせをしていただきました。
読み聞かせは、子どもの成長にたくさんの栄養と影響を与えます。
同じ空間で読み聞かせを聞くことは、画面を通して本の朗読を聞くこととはまったく違うと感じます。
人の声の持つ力、ぬくもりが、聞いている子どもたちに伝わるからでしょう。
本の世界に浸る子どもたちの表情が印象的でした。
心地よいひととき
本の世界に引き込まれています
授業研究会(7月1日)
6月28日金曜日、今年度第1回目の授業研究会を行いました。
2,3年生と4年生が算数の授業を公開しました。
今年度の研究テーマは「主体的に学ぶ子どもの育成」です。
子どもたちは、課題に対して主体的に取り組み、友達と支えないながら粘り強く考えることができました。
授業後の話し合いでは、子どもたちの思考の様子や教材の効果、交流方法について話し合いを行いました。
これからも、皆で話し合いながら、子どもたちが主体的に学び、力を伸ばせる授業づくりを進めていきます。

0.01をもとにして考えるから…

ICTを活用して考えを共有します
自分の考えを説明する(6月27日)
自分の考えを人に説明する力は、いつでも、誰にとっても必要です。
それは、家にいても学校にいても社会に出ても同じ。
そのくらい大切で基本的な力です。
でも、子どものたどたどしい説明に耐え切れず、大人が先回りをして「○○でしょ」と言ってしまうと育ちません。
だから、聞き手には「待つ力」「聴く力」が求められます。
今日の1年生の教室。「たし算のきまりを見つけよう」という学習をしていました。
見つけたきまりを一生懸命に説明する友達の言葉を一生懸命に聞く子どもたちです。

数字を横に見ていくとね…

ななめに見ると、こうなっているよ。
「わからなさ」が考えを深める(6月26日)
「わかる」「できる」ことは気持ちがいいです。
反対に「わからない」ことは、気持ち悪く、落ち着かないもの。
けれども、何かを学ぶとき、「わからないのにわかるふりをする」のは決してしてはいけないこと。
それをやってしまうと、学びは止まってしまいますし、まったく楽しくなくなります。
「わからなさ」を楽しむ。「意見の違い」を味わう。
心の強さが必要ですが、それができると、考えが格段に深まります。
「わからない」と言ってくれる友達のおかげで、「え、どうしてそうなるの」と訊いてくれる仲間のおかげで、学びは豊かに広がり、深まり、楽しくなります。

ねえ、どうして?

一人の疑問をみんなで考える
鍵盤ハーモニカ講習会(6月25日)
6月24日、1年生を対象に鍵盤ハーモニカ講習会を行いました。
専門の先生に教えていただいたので、鍵盤ハーモニカを演奏するときに大切なことを、すっきり楽しく学ぶことができました。
上手に音が出せるようになり、みんな笑顔です。

説明を一生懸命に聞いています

真剣な表情です
テキストを媒介にして考える(6月24日)
協動的に学ぶ、というと「話し合い」をイメージしますが、それだけではありません。
実は「きき合う(聴き合う、訊き合う)」ことが対話の土台になります。
互いの顔を見て意見を出し合うのではなく、教材を媒介にして、互いの考えをきき合うのです。
国語の「読む」活動ならば、テキストを媒介にして考えます。
互いの声に耳を傾け、一人ひとりが考えて、それぞれが考えを深めています。

こう書いてあるから…

僕はこう考えたんだけど…
ICTで考えを共有する(6月21日)
自分の考えを友達と共有するとき、従来は紙やミニホワイトボードに書いて黒板に貼る、ノートを実物投影機でテレビに映すなどの方法がありました。
けれども、今、子どもたちは一人一台の学習用タブレットを持っています。
これを活用すれば、今までよりずっと簡単に、一人一人の考えを一度に提示して全員で共有することができます。
今日は、ICT支援員の方の力も借りて、2,3年生が、一人一人が撮影した写真をクラスみんなで一度に共有する、という活動をしました。
この方法を身に着けた子どもたちが、学びにどう生かしていくのか楽しみです。

すごい、これ誰が撮った写真?

このように共有されます
初めの一冊、全校読書(6月20日)
今日は、村山市から、1年生一人一人に「はじめの一冊」が贈られました。
前もっておうちの人と相談しながら選んだ一冊です。
本をいただいた子どもたちは、とてもうれしそう。
「ありがとうございます!」とお礼を言うと、すぐにページを開いて読み始めていました。
また、今日は全校読書も行われました。
30分間、学校にいる全員が静かに本を読みました。
いい時間が流れていました。
本は心の栄養ですね。

はじめの一冊贈呈

みんな静かに本を読む
5,6年租税教室(6月19日)
今日は、外部講師をお招きして、5,6年生を対象に租税教室を行いました。
子どもたちは、アニメーションやスライドで、税金の使い道や税金がないとどうなるのかについて学びました。
身近なところにも税金が使われていること、税金のおかげで快適で豊かな暮らしができることを知りました。
学校で学べるのも税金のおかげ、もし税金がなかったら…大変です。

税金がなかったら…

学校で授業を受けるのにかかるお金は…
3年枝豆植え(6月18日)
6月17日、3年生が伝承館の畑に出かけ、枝豆を植えてきました。
秘伝など、数種類を植えました。
昨年度は猛暑のため、不作だったとのこと。
今年も暑さが心配ですが、元気に育ってほしいです。

植え方を教えていただきました

元気に育ってね
不審者対応訓練(6月17日)
6月14日に不審者対応訓練(連れ去り事案)を行いました。
校外で知らない人が児童に声をかけ、ものをあげるとか、道を教えてほしいなど言葉巧みに近寄り、連れ去ろうとする、という設定です。
ついて「いか」ない
車に「の」らない
「お」おごえを出す
「す」ぐにげる
大人に「し」らせる
という「いかのおすし」を復習した後、児童に不審者に扮した方が声をかけ、そういうときはどうするか、というロールプレイングで学びました。
まず、手の届く距離に近寄らない、ということも大切だとわかりました。
命は一つです。万が一の時に自分の命を守れるように、繰り返し訓練していきます。

声をかけられても…

体をつかまれないようにそばに寄らないこと
1,2年地区たんけん(6月13日)
1,2年生が生活科の学習で、地区たんけんに出かけました。
今日は、土生田地区を回りました。
子どもたちは、気になる場所の写真を撮ったりメモをしたりして一生懸命調べました。
時々休憩をはさみ、地区の方にもお話を聞きました。
学校の前を羽州街道が通っていたという標を見つけた子どもたち。
もう少し学年が上がれば、この標の意味がわかるようになるでしょう。
袖崎地区は交通の要衝だったのですね。

ふたば袖崎保育園の前でパチリ

なんて書いてあるの?
プール清掃(6月12日)
今日は、全校生みんなでプール清掃です。
プールの中は4‐6年生が担当。落ち葉がたくさん溜まり泥状になっているため、なかなか大変です。
底面、側面ともたわしやデッキブラシ、ワイパーを使って一生懸命磨きました。
プールサイドの担当は1‐3年生。たまった砂やほこりを丁寧に掃きました。
力を合わせて働いたので、1時間ほどできれいになりました。
きれいになったプールで水泳授業。楽しみです。

砂がたまっているね

ごしごしごし
運動会フォトギャラリー(6月11日)

よーいどん!

もっと入れ!

行くよ!

おっとっと
成長を感じます(6月11日)
今日は、気温が29度近くまで上がり、子どもたちも汗をかきながらの活動です。
1年生は、帰りの会で連絡帳を書いていました。4月に比べ、字がすらすら書けるようになっています。
4年生は、社会「水はどこから」の学習です。村山市の人口と水道使用量からわかることを考えています。
運動会明けでも暑くても真剣に学んでいます。

1年生 帰りの会

4年生 社会
運動会(6月8日)
今日は運動会です。
これまで、34人みんなの力を合わせて、準備を進めてきました。
その成果を発揮する日です。
学年が上がるごとに力強くなる100メートル走。
練習とは結果が違った団体種目。
声を限りに顔を真っ赤にしながらの応援。
嬉しさはじける笑顔、悔しさで呆然とする表情。
どの顔も真剣さに満ちていました。
一人一人が成長できた運動会でした。
保護者の皆様、地域の皆様のご協力、ご声援、ありがとうございました。

恒例の仮装花笠(飛び入り)

とるぞ!V2

声を合わせて心を合わせて
本番前最後の応援練習(6月7日)
いよいよ明日は運動会です。
今日は、赤組白組それぞれに最後の応援練習を行いました。
応援合戦の動きの確認、個別の声掛け、そして明日に向けて気合を入れます。
がんばるぞー!オー!
保護者の皆様、地域の皆様、明日は子どもたちの頑張る姿をぜひご覧ください。

ワー!!ドドドドン!

回ってジャーンプ!みんなできているかな?
運動会総練習(6月6日)
今日は、運動会総練習です。
開閉会式練習、応援合戦、綱引き、花笠踊り、リレーの練習を行いました。
練習とはいえ、上級生が声を出して下級生をリードし、下級生も一生懸命にそれに応えていました。
子どもたちの本気が伝わってきました。
本番が楽しみです。

そーれ!そーれ!

接戦!
ユリノキ班種目練習(6月5日)
今日は、運動会で行う、ユリノキ班(縦割り班)の種目練習を行いました。
今年度は、30個のまりをどれだけ早く運ぶかで競い合います。
ボードに1から3個のまりを乗せ、けんけんぱをしたり、輪の周りを回ったり、輪をくぐり抜けたり。
振動でまりが落ちてしまうので、なかなか難しいです。
走るのか歩くのか?何個乗せるのか?回るときはボードをどう傾けるか?
班ごとの作戦とチームワークの勝負です。

傾けたほうが…

おっとっと
手を動かして学ぶ(6月4日)
話を聞く、教科書を読むだけではなく、手を動かして学ぶと理解が深まります。
3年生は、粘土で昆虫をつくっています。昆虫の体の構造がよくわかっていないとつくれません。
4年生は、保健室に来室した理由のデータに印をつけて数え、整理しています。そのあと、正確を期すためみんなで数を確認しています。

えーと、カブトムシは…

切り傷の数は?
花笠踊り練習(6月3日)
今日は、運動会に向けて花笠踊りの練習を行いました。
まず、ユリノキ班ごとに上級生が下級生に教えました。初めての1年生にも優しく教えてくれました。
踊りの動きが理解できたところで、みんなで輪になって踊りました。
「ヤッショーマカショ 袖崎小 それ!」

こうやって踊るんだよ

花笠音頭に乗って
升川建設さんのご厚意で国旗掲揚塔が復活(5月31日)
長年、旗をつけるロープがなくなっていたため、使用できなかった国旗掲揚塔。
今回、升川建設さんのご厚意で、掲揚塔にロープを取り付けることができました。
おかげさまで、運動会には旗を掲揚できそうです。
大変ありがとうございました。

高所作業車で…

15メートルの高さに取り付け
里芋を植えました(5月31日)
今日は、1,2年生が畑の先生のご指導の下、里芋の苗を植えました。
品種は「土垂」だそうです。
小雨がぱらついていたため土が濡れて、泥だらけになりながらもがんばって植えました。
秋に収穫し、芋煮会をして食べられるように、水かけなどの世話に取り組みます。

うーんと、この種芋を…

ここに植えるよ
運動会練習(台風の目)(5月30日)
運動会競技の練習が本格的に始まりました。
今日は、初めて4年生が「台風の目」に挑戦しました。
いろいろな動きが組み合わされた競技、はじめは少し難しかったようですが、息を合わせて頑張りました。

ジャーンプ!

遠心力に負けるな!
運動会結団式・応援練習開始(5月29日)
昨日、運動会の結団式が行われました。
子どもたちが話し合って決めたスローガンは、「全力協力!!34人の力を見せつけろ!!ー思いやりの運動会ー」です。
今日は、赤白に分かれて応援練習が始まりました。
応援団は、下級生に応援の振り付けや声の出し方を説明したり、手本となって大きな声を出したりしていました。
今はまだ、うまくいかないところもありますが、6月8日の運動会本番に向けて毎日準備と練習に取り組みます。

結団式

赤組の応援練習

白組の応援練習
ふれあい見守り員顔合わせ(5月28日)
5月27日、地域のふれあい見守り員さんとの顔合わせがありました。
子どもたちの安全な登下校のために、雨の日も雪の日も猛暑の時も、見守りをしてくださっている皆さんです。本当にありがとうございます。
また、村山警察署の方からは、声かけ事案に対する注意喚起とマジックによる交通安全指導をいただきました。
命を守るために、いつも心にとめておきたいです。

子どもたちから感謝の言葉を伝えました

いかのおすし 覚えているかな
数の分解・合成を楽しく学ぶ(5月27日)
1年生の算数の学習です。
合わせて8になるように、二人で同時に数のカードを出します。
「せーの!」
「わあ!やった!8になった。」
「これじゃ2だね…(苦笑い)」
楽しく学びながら、数の分解・合成を理解しています。

いっせーの!

はい!
授業風景(5月24日)
5,6年生の道徳、「捨てられるペットが大変多いことについてどう思うか」
「ひどい。かわいそう。」
「途中で捨てるなら飼わなければいい。」
「でも、飼い主にも事情があるのかも…」
簡単には答えの出ない問題について考えています。
1,2,3年生の生活科、一人一人が作った春クイズを出題。
「ええ、わかんない。」
「答えは…ひばり!」
「えっ!ひばりって?」
見たことがない鳥だったようです。
4年生はALTの先生と外国語の学習。
先生の後に続いて、曜日と食べ物の発音を繰り返し練習しました。

1、2、3年生

5,6年生

4年生
スポーツテストを行いました(5月23日)
5月23日、スポーツテストを行いました、
測定種目は、反復横跳び、上体起こし、立ち幅跳び、長座体前屈、握力、50メートル走、ソフトボール投げ、シャトルラン。
この中で比較的新しい種目はシャトルランです。持久力を測定します。
20メートルの間を音楽に合わせて何往復できるかを測るのですが、その音楽はだんだん速くなっていきます。
みんなで応援しながら、頑張りました。
この測定結果をもとに、子どもたちは自分の体力を知り、めあてをもって運動することにつなげます。
シャトルラン
5分間マラソン開始(5月22日)
ユリノキの花が咲くグラウンドで、昨日から5分間マラソンが始まりました。
5分間というのは意外に長い。でも、子どもたちは音楽が流れている間、一生懸命走っています。
さわやかな5月、運動するのに最適な季節です。

がんばれ!もう少し

ユリノキの花 満開です
自分(たち)で学ぶ(5月21日)
複式学級では、自分(たち)で学ぶ時間が多くあります。
4年生は、都道府県の特色を説明した文章の漢字の読み方がわからず、自分(たち)で漢字辞典を使って調べていました。
「ええと…あった!」
「べいさくって読むんだ!」
わかった瞬間の子どもたちの笑顔を見て、こちらもうれしくなりました。

よねさく?べいさく?
リコーダー講習会(5月20日)
今日は、外部の講師の方をお招きして、リコーダー講習会を行いました。
まず、息の吐き出し方から。そして、リコーダーの持ち方、息の吹き込み方、指使いへと段階的に進みます。
わかりやすく教えていただいたので、いい音を出せるようになりました。
これからいろいろな曲を演奏できるようになると、ますます楽しめそうですね。

風船を膨らませるように息を出します
子ども農楽校でサツマイモを植えました(5月17日)
5月17日、村山市農林課主催事業子ども農楽校の活動で、1,2年生が農村文化保存伝承館の周辺の畑に出かけて、サツマイモの苗を植えました。
講師の方に教えてもらいながら、丁寧に植えました。
少し風が強かったけれど、頑張って200本くらい植えました。
元気に育ちますように。

土をかけて…
村山市陸上競技大会出場(5月16日)
今日は、村山市陸上競技大会が行われました。
本校からの出場選手は、5,6年生7人です。
練習したことを発揮し、持てる力を出し切った一人一人。
全力を尽くす姿は、本当に輝いています。
よく頑張りました。

イチ、ニ、サン!

それっ!

えいっ!

めざせ自己ベスト!

ここからだ!

スタート!

行くぞ!

みんな頑張ったね
社会を学ぶ(5月15日)
社会科は、自分を取り巻く社会について学ぶ教科です。
4年生は、山形県の地図を見ながら交通網について話しています。
「山形県に空港2つあるんだ!」
「高速道路のICはわかるけど、SAって?JCTって?」
5年生は、ほかの地域の地理について、6年生は政治の仕組みを調べていました。

5年生

6年生

4年生
市陸上大会壮行式(5月14日)
今日は、5月16日に行われる市陸上競技大会の出場選手を激励するため、壮行式が行われました。
まず、選手一人一人が、自分の出場種目と目標を述べました。
そして、4年生が中心になって作り上げてきた1年生から4年生の応援です。
声が大きく、力強く、キレのある応援。「がんばって!」と言う下級生の気持ちがひしひしと伝わってきました。
きっと、選手の皆さんは大きな力をもらったことでしょう。
大会では、今までの練習を生かし、ぜひ自己記録を更新してほしいです。

私の目標は…

気合いの入った下級生の応援
読むこと・書くことは学びの基礎(5月13日)
言うまでもなく、読み書きは学びの基礎です。
小学校はその基礎を身につけるところ。
子どもたち、真剣に学び、練習しています。

教科書の音読、暗唱

ひらがなの練習

数字の練習
市陸上競技大会壮行式練習(5月10日)
来週の5月16日(雨天17日)に市の陸上競技大会が開催されます。
今日は、1年生から4年生が陸上競技大会のための壮行式練習をしました。
4年生が中心になり、力いっぱい声を出して下級生に教えました。

見本を見せます

フレ!フレ!
アナログもデジタルも(5月9日)
学ぶために調べ物をする、記録をとる、その方法はアナログ、デジタルそれぞれに良さがあります。
漢字の意味や使い方を調べるために漢字辞典や教科書を使う。
同じ部首が付く漢字を探すために友達に訊く。
朝顔の観察記録をタブレットのカメラで撮る。
これからは、多様な解決方法を知り、時と場合に応じて選ぶ力をつけることが必要です。
そのためにも、子どもたちは日々学んでいます。

5年生(漢字の意味と使い方を調べる)

6年生(肉月のつく漢字は…)

1年生(タネをまいたばかりの様子を記録)
緑の少年団結団式・花いっぱい運動(5月8日)
今日は、緑の少年団結団式を行いました。
そのあと、花いっぱい運動として、ユリノキ班で花植えを行いました。
緑の少年団のちかい「緑に親しみ、緑を愛し、緑を守り育てる」
言うは易し、行うは難しです。
今日植えた花に水をかけた5,6年生が、その大変さを実感していました。
子どもたちが緑を守り育てる活動、これから楽しみです。

緑の少年団旗授与

土に穴をあけて…
支え合い、学び合う(5月7日)
学校の毎日は、初めて挑戦することだらけです。
初めてのことはだれでも不安。そんな時、そばに仲間がいてくれると心強い。
何も話さなくても、隣にいてくれるだけで力がわいてきます。
互いの意見を聞きながら考えれば、さらに学びは深まります。

一緒に考えよう

漢字の練習がんばるぞ

ええと、これを…

図にかいて考えてみたよ
JRC加盟式(5月2日)
JRCの加盟式を行いました。
袖崎小では, JRC活動について学ぶこと,新入生である1年生がJRCに加盟すること,全校児童がJRC活動について気持ちを新たにすることを目的に毎年加盟式を行っています。
青少年赤十字活動の態度目標「気づき 考え 実行する」は、袖崎小の今年度のテーマ「自分(たち)で決め、行動する」にぴったりです。
今年度も、様々な活動を通して、「気づき 考え 実行する」態度を身につけていきたいと思います。
今日は、新たに加盟する1年生に、ワッペンを渡しました。

青少年赤十字の旗の入場

1年生にワッペンを渡しました

ちかいの言葉
じっくり考える、無心に表現する(5月1日)
4年生は国語の物語文の読み取り。物語全体にかかわる難しい課題について考えています。
2,3年生は、図工で自分の好きなものを描いています。集中していることが伝わってきます。
子どもたちの様子から、考えること、表現することの喜びが感じられました。

ええと…

こう書いてあるから…

真剣な表情

無心に描く
1年生を迎える会(4月30日)
今日は、4,5年生が企画、運営を行う1年生を迎える会がありました。
みんなの笑顔と手拍子に迎えられて1年生入場。
4,5年生が飾り付けてくれた会場で、「学校クイズ」「1年生へのインタビュー」「1年生から自己紹介と校歌」「1年生への各学級からのプレゼント」と続きます。
本格的な「学校クイズ」では1年生と一緒に楽しみ、一人一人の好きなものや将来の夢を聞く「1年生へのインタビュー」では1年生のことをもっと知ることができました。
また、元気いっぱいの1年生の自己紹介や校歌を聞いて、2年生から6年生は、感心したり驚いたりしていました。
最後に、各学級からのプレゼントです。
5,6年生は、スイーツとポケモンの手作りキーホルダー。
4年生からは、紙で作った色とりどりの花束。
2,3年生からは、豪華なメダル。
もらった1年生は、目を丸くして受け取り、嬉しそうにずっと見ていました。
みんなの1年生を思う気持ちが詰まった素敵な会でした。

学校クイズ「さあ、1年生わかるかな?」

わかった!

はい!はい!はい!はい!

いえーい!(盛り上げる)

好きな動物は、リスです。

将来は警察官になりたいです。

わあ、すごい!

これからもっともっと仲良くなろうね
陸上競技練習始まりました(4月26日)
昨日から、5月に行われる市小学校陸上競技大会に向けて、放課後練習が始まりました。
出場対象は5,6年生ですが、練習は4年生も一緒に行っています。
今日は、自分がやりたい競技に取り組みました。
それぞれが集中して練習し、初日から大会出場標準記録突破も出て、
「すごい!」「やったね!」
とみんなで喜び合いました。

それっ!

イチ,ニ,サン!

跳べた!

行くよ!

ジャーンプ!

あそこまで飛ばすぞ!
ALTと外国語の学習・社会の調べ学習(4月25日)
今年度初めて、ALTの先生と一緒に外国語の学習をしました。
今年度から新しくいらっしゃったALTの先生の自己紹介を聞いた後、「好きなスポーツはなんですか」「(うどんが好きと聞いたので)好きなうどんは何ですか」などと質問をしました。ちなみに、冷たいうどんが好きなんだそうです。
早く仲良くなって、積極的に会話ができるといいですね。
5,6年生の社会科の学習。
5年生は、日本の国土の特徴を資料集の写真を見ながら考えています。一方、6年生は、基本的人権について、教科書を読んでノートにまとめています。
真剣に考えていることが伝わってきました。

おお、冷たいうどんが好きなんですか。

海に囲まれているんだなあ

基本的人権とは…
自分が関わる学びは楽しい(4月24日)
3年生の国語の学習。教科書で読んだ物語の続きを自分(たち)で考えて書きました。
今日は、それを読み合っています。読んでいる人も聞いている人もうれしそうです。
1年生は図工「どんどんかくのはたのしいな すきなものなあに」の学習です。
タイトル通り、自分の好きなものをかくのは最高に楽しそう。いい表情です。

おお、面白いね

どんどんかくぞ

すきなもの、もっとかきたい
春のうさぎ山

木々の芽が萌え出す春。ウグイスの声が響きます
ICTを道具として使う(4月23日)
一人一台のタブレットに加えて、教室には電子黒板が整備されています。
4年生では、デジタル教科書を使って、電子黒板に「位取り表」を大きく映して学習していました。
以前は、教科書を拡大コピーしたり、大判ラシャ紙に位取り票を書いて色を塗ったりしたものです。
それが、デジタル教科書を使えば、一瞬で提示できる上に、児童用教科書と全く同じ画面なので、子どもたちは指している場所がつかみやすいのです。
また、2年生は、春になるとみられるものを探して、言葉と絵でカードにかいていました。
いろいろな春のものの絵をかく時、実際に探しに行かなくても、タブレットの画面上で見ることができます。
実物を見るのも大切ですが、限られた時間の中で多くの情報を集めることができるのは、ICTのよさだと思います。

電子黒板で位取り表を提示

えーと、この花は…
地域の方にお花をいただきました(4月23日)
地域の方に、色とりどりのクリスマスローズを頂戴しました。ありがとうございます。
早速、玄関前に飾らせていただきました。

シックな色合いが素敵です
真剣に調べる、考える(4月22日)
6年生の理科です。
酸素、窒素、二酸化炭素の性質を調べています。
火がよく燃える気体と消えてしまう気体、どれだろう。
「あっ!消えた。」
「なんで?さっきは燃えてたのに…」
最初からろうそくの火が消えてしまう気体もあるけれど、初めは火が明るく燃えるのにしばらくたつと消えてしまう気体もある。なぜ?
新たな疑問が浮かんだようです。

あ、消えた。

あれ?さっきは…
授業参観・PTA全体会・学級懇談会(4月19日)
今日は、入学・進級して初めての授業参観。子どもたちはおうちの方がいらしてくださったので、いつも以上に元気いっぱい。はりきって学習しました。
授業参観の後は、PTA全体会と学級懇談会が行われました。お忙しい中、ご参加ありがとうございました。

1年生

2,3年生

2,3年生

5年生

6年生

4年生

PTA全体会
仲間と一緒に学ぶ(4月18日)
袖崎小学校の目指す子ども像の中に「最後までやり抜く子ども」「進んで学ぶ子ども」があります。
一人でできることも、もちろん大切ですが、仲間と一緒なら、何に対しても一層意欲がわき、あきらめず粘り強く取り組むことができます。
今日は、仲間と一緒に学ぶ素敵な姿をたくさん見つけました。

本に書かれている番号はね…(学校たんけん)

ねえ、どうしてこうなるの?(算数)

元気いっぱい、校歌の練習です
5,6年社会の学習(4月17日)

地図帳やネット検索を使って調べます

日本国憲法について動画で学びます
1,2,3年合同体育(4月16日)
1,2,3年生は、合同で体育をしています。今日は、ボールを使ったリレーをしたり、鬼ごっこをしたりして、多様な動きを取り入れた学習をしました。
最後の手つなぎ鬼では、みんな力いっぱい逃げて追いかけて、明るい声と笑顔がはじけていました。

わあっ!逃げろ!

鬼はどの辺かな?

あ!あの人がいい、行くよ!
あたたかくなると(4月15日)
校庭の桜が満開を迎えています。ここ数日季節外れに気温が高いので、早くも桜吹雪になりそうです。
4年生の理科では、「あたたかくなると、植物や動物の様子はどう変わるだろうか」という学習をしています。
今日、子どもたちは外に出て、各々自分の選んだ植物の観察をしました。じっくり見ながら観察カードに植物の様子をスケッチしていました。


パンジーをよく見ると

ええと、この花の名前なんだっけ

白と黄色がきれいだなあ
PTA作業(4月13日)
4月13日(土曜)PTA作業があり、雪囲い撤去作業やフェンス設置、側溝の泥上げや掃除等の環境整備が行われました。今年は天候がよく、満開の桜の下の作業となりました。おかげ様で子どもたちの学習環境が整いました。

避難訓練・ユリノキ班清掃開始・学習風景(4月12日)
命を守る避難訓練
今年度初めての避難訓練を行いました。
調理室から出火した想定で、子どもたちは、学習を行っていた場所から、指示に従い、昇降口前の一次避難場所に集合しました。
全員の避難完了を確認後、火が燃え広がっているという想定で、二次避難場所に移動しました。二次避難場所はグラウンド南側です。
子どもたちは、指示(放送)をよく聞き、静かに落ち着いて行動することができました。「押さない」「走らない」「しゃべらない」「もどらない」の約束もきちんと守れたと思います。
どこでどんな災害に遭遇するかわかりません。万が一の場合、命を守る行動がとれるように訓練を重ねていきます。
ユリノキ班(縦割り班)清掃開始
今日からユリノキ班清掃が始まりました。上級生も下級生も力を合わせて清掃に取り組みました。


学習風景(5,6年)
総合の学習で、修学旅行の班別研修の行き先を考えるため、いろいろな施設や交通手段を調べました。


桜ほころぶ春 学習とグラウンド整備(4月11日)
桜が咲き始めました

学習風景(1年生)おはなししよう かぞえよう
1年生の学習、一人一人のやる気と元気があふれています。

気づいたことは何かな

もっとあります
ユリノキ班でグラウンド整備
グラウンドの状態が良くなかったため、今日に延期されたグラウンド整備。子どもたちは、一生懸命小石や枝を拾い集め、みんなが使うグラウンドを整備しました。

あ、ここにもあった
青空の下 元気に登校(4月10日)
登校班での登校 班長さん頑張っています
昨日とはうって変わった青空の下、子どもたちは今日も元気に登校しました。入学したばかりの1年生の歩みを気遣い、自分もゆっくり歩く上級生の姿が見られ、ほほえましく頼もしく感じました。






今日は鳥海山もきれいに見えました(児童会室より)

授業風景・給食・集会(やくそく)(4月9日)
授業風景
新学期の授業が始まりました。みんな真剣に学んでいます。

2,3年生

4年生
給食が始まりました
今年度最初の,1年生にとっては初めての給食です。今日のメニューはカレーライスとフルーツポンチ。みんなおいししくいただきました。

カレー大好き!

おいしいね
集会(やくそく)
学校生活に関わる約束について集会でお話がありました。この約束を守って、みんな安全に楽しい学校生活を送れるようにしたいです。集会の最後には、袖崎小学校で大切にしている「洗心あいうえお」を確認しました。

集会の様子

やくそくと洗心あいうえお
新任式・始業式
新任式
今日から令和6年度の教育活動がスタートしました。新任式では、新しく3名の先生を迎え、代表の6年生が歓迎の言葉を述べました。

新任式
始業式
始業式では、教科書が校長から6年生の代表児童に手渡され、そのあと、「今年度児童の皆さんに頑張ってほしいこと」の話と担任発表がありました。

始業式
入学式
今年度は8名の新入生を迎えました。新1年生のみなさんは、笑顔で入場し、名前を呼ばれると元気よく返事をすることができました。話の聞き方も大変上手でした。これからみんなで楽しい学校生活をつくっていきたいです。

新入児童呼び上げ

校長式辞

学校生活について発表

集合写真